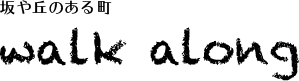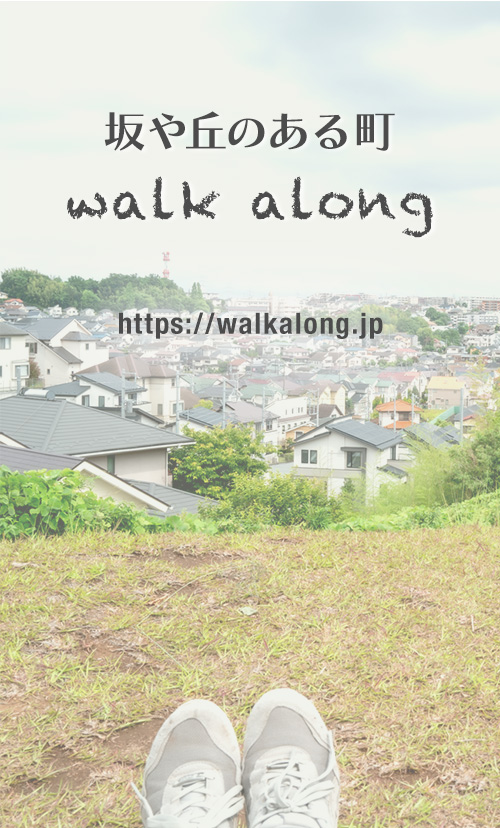ベランダでコンポスト、とってもカンタン!土とぬか、生ゴミを混ぜるだけ。家にあるものでできちゃうよ

ベランダで植物を育てていると気になるのが土のリサイクル。
毎回土を買ってきて、栽培が終わったら土を捨てる。
もったいないなあ、、と思いながらも、土の使い回しは虫や病気の発生に繋がるので、仕方がなかった。
しかし!
コンポストを始めたら古い土がふかふかの堆肥になった!
生ごみも激減。
バケツや段ボールに新聞紙を敷いて土とぬかを入れたら、生ごみを混ぜて時々水をやるだけ。それだけで、微生物が生ごみを分解・発酵して堆肥に変えてくれる。
な〜んて、魔法じゃあるまいし。信じられない。
でもでも、できるんです。できたんです。
マンションのベランダで!
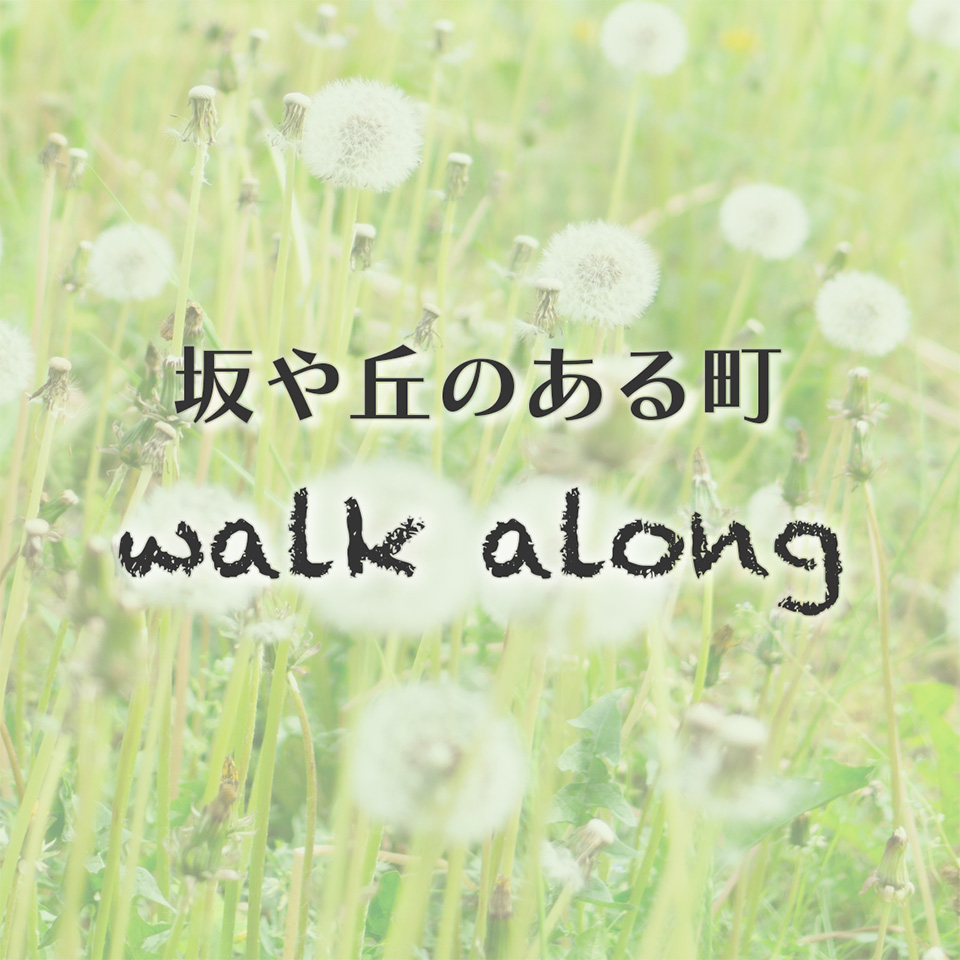
記事執筆 & 写真撮影 青山田あかり
神奈川県 横浜市在住。写真ブログ「坂や丘のある町 walk along」に、気楽な記事を毎週投稿しています。
コンポストづくりの手順
- 容器の底に新聞紙を敷く
- 土とぬかを10:1程度の割合で混ぜる。これが「基材」。
- 新聞紙の上に、5センチほど基材を入れ、生ごみを投入
- 生ごみが隠れるように基材をかぶせる
- ちょっぴり湿るぐらいの水をかける
- 空気が入る素材のフタ(布など)をする
- なるべく風通しがいいところに置く
- その後毎日生ごみを投入し、基材と混ぜ、生ごみが隠れるように基材をかぶせる、を繰り返す
- 容器がいっぱいになったら生ごみの投入をやめて、1〜2カ月熟成させる(夏は早く、冬は遅い)
- 堆肥ができる!
参照:「コンポストのメリット・デメリット、作り方・使い方まで!ベランダやお庭で簡単・おしゃれに自作の生ゴミ堆肥づくり【農学専門家執筆】」
コンポストは未知の世界
コンポストって始めるまでが一番ハードル高いかも。
街中に暮らす一般人にはコンポストって想像もつかない未知の世界ですよね。それも、マンションのベランダでチャレンジするなんて。
始めるまでのワタクシのイメージは、、
- 高価な専用容器や専用の土がないとできない
- 毎日の手入れにものすごく手間がかかる
- 悪臭がしたり、ウジ虫がわく
- 微生物?そんなものどこからくるの
って感じで、コンポストは「園芸マニアの高級な芸ごと」みたいに思ってました。
そんな時ネットで目にした記事を読んで、「あれ?なんか、カンタンにできそう、、?」と思ったのがスタートのキッカケです。
実際の様子は記事の続きをご覧あれ。
結論として、家にあるものでカンタンにできて、悪臭もしないし、ウジ虫もわかなかった(ウジ虫が出たとしても、発酵を助ける役割があるそう)。微生物はしっかりどこかから出てきて、せっせと生ごみを分解してくれてます。1日に一度、コンポストを混ぜるのは、ぬか漬け作りと似ています。一回数分程度で、手間もかかりません。
関連記事:驚きの現代ぬか漬け事情|マイぬか床、やってみました!
コンポスト用の容器は何を使う?
コンポストを始めるにあたって最初の難関は、どんな容器を使うのか。
参照した記事によると、「バケツ、段ボール、ペットボトル、チャック付きポリ袋」など身近なものを利用してコンポストができるらしい。
ちょうど、フタつきの漬物用容器があったので「バケツコンポスト」の代用として使いました。
左上から時計回りに、「(漬物用)容器」、古い土、新聞紙、生ごみ、ぬか。ぜ〜んぶ、うちにあるものでコンポストがスタートできる!

コンポストづくり、始めるよ!
まずは容器の底に新聞紙を敷きます。

古い土とぬかを10:1で混ぜます。これが「基材」と呼ばれるもの。

買った腐葉土でももちろんOK。腐葉土が培養土(肥料入りの土)になりますね。
土とぬかを混ぜると、こんな感じ。ぬかの粒々が土に混ざって全体的に白っぽくなりました。

底から5センチぐらいの深さに基材(土)を入れたら、生ごみ投入!
生ごみは、硬貨大ぐらいまで細かくした方が早く分解されやすい。玉ねぎの皮や、固い骨、種などはなかなか分解されません。魚や肉は腐敗する可能性あり。ワタクシは入れませんでした。

生ごみが隠れるくらい、基材をかけます。

最後に「たらたら」っとジョウロから水を垂らして、ちょっと湿らせます。

空気を通すため、フタにキリで穴をあけました。フタがないバケツなら、布を被せてフタがわりに。

残りの基材も「ふるい」などを被せて、虫が入らないように防御します。

これで終了!
あとは、毎日生ごみを入れて、混ぜて、基材をかける、を繰り返すだけ。カンタン!
2週間後、容器がいっぱいに
毎日生ごみを投入し続けて、約2週間。
フタに水滴がつくようになり「微生物が呼吸してる」感じになってきました。

土を混ぜてみると、まだ生ごみは分解されていません。

ここから約1〜2カ月の熟成期間スタート。
生ごみの投入をやめて、フタをしたまま置いておきます。
1週間に一度ぐらい、底から上下を返すように土を混ぜ、ちょっと湿るだけ水を追加。

開始から約1カ月。白カビ発生で、コンポスト成功!
コンポストを初めてから約1カ月、熟成期間に入って約2週間。土の表面にクモの巣状の白い細い糸のようなものが発生。白カビです。

この白カビが発生すると、発酵が順調に進んでいる合図なんだそう。やった〜
コンポストの中に指を入れてみると、ほのかに暖かい。発酵が進むと基材の温度が上がって、40°〜60°ぐらいになるらしい。
匂いを嗅いでみると、雨の日の森のような、深い土の香り。全然悪臭なんかじゃない。
土を握ってみると、かたまりになってからホロっと崩れていく。カチカチでザラザラだった古い土が、しっとり、ふかふかの土に生まれ変わっていました。
コンポストは、2台で回していくよ
1台目が熟成中は、2台目に生ごみを投入。2つのコンポストを順番に使って、うまく回していければいいな。

ベランダで野菜づくり
1台目のコンポストで堆肥が熟成完了する頃は、ちょうどじゃがいもの植え付け適期(関東では3月上旬〜4月中旬)。コンポスト堆肥を使って、ベランダでのじゃがいも袋栽培に挑戦する予定です。
コンポスト堆肥は効果が穏やかなので、化成肥料を追加して用土を調整してみます。
コンポストすご〜い
始める前は、まったく信じていなかったコンポスト。
しかし、毎日生ごみを入れて、基材を混ぜて、様子を観察して、、とやっているうちに「土って元々こうやって循環しているものなんだな」と納得。
ワタクシは2台のコンポストを回していますが、適当におおらかにやっていても全く失敗する感じがしません。
土に養分を持ったものを投入すると、どこからか微生物が集まってきて一生懸命分解してくれる。すると土は喜んでエネルギーを発散させて(発酵)、また生物を育てる土壌として復活する。そういうものなんだな〜、と。
なんか、自然ってホントにすごい。
自然の営みが、あの漬物容器の中でも循環しているなんて。
便利で効率的な社会に暮らしていても、人間は大きな自然の中で生かされているんだな〜、と改めて考えさせられてしまったコンポストづくり。
すごい!